柱が立ち、屋根がかかり、家らしくなってきた大工作業も一段落。
ここからはいよいよ左官作業の始まりです。
まずは「竹小舞(たけこまい)」という日本の伝統的な工法で、割った竹を格子状に組み、土壁の下地を作っていきます。
左官職人の方が縦の竹を柱に取り付け、私たちはその間に横の竹を紐で編み込んでいきました。
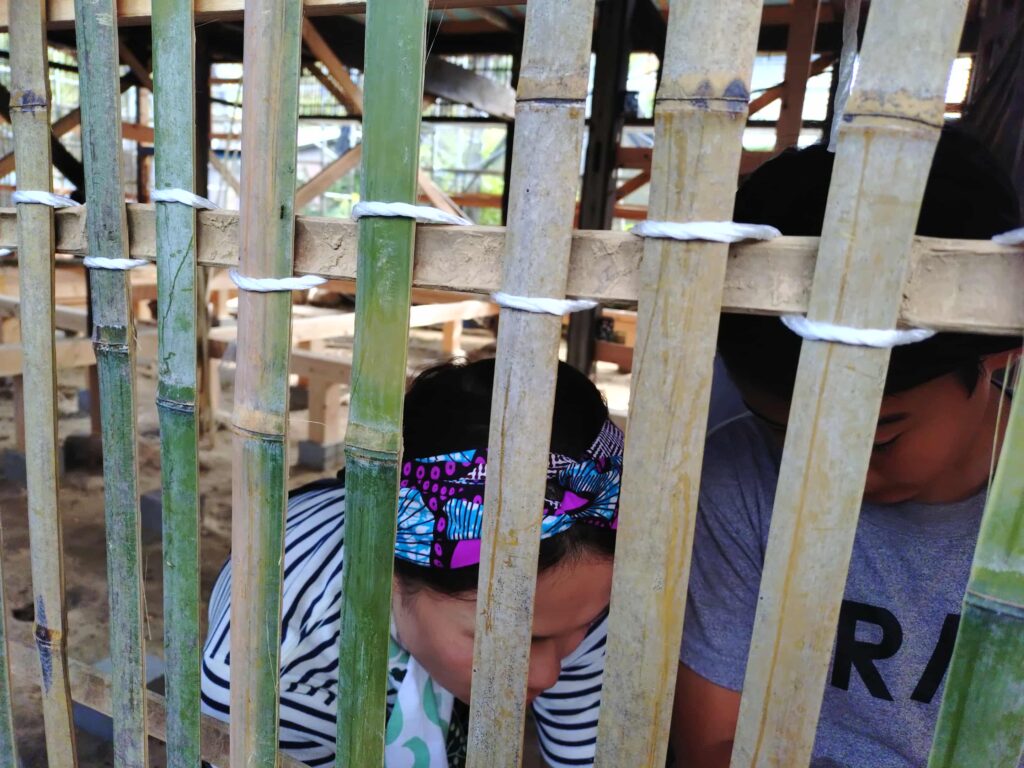

竹を横にして、紐で結んでいきます。
上から上へ、下から下へ――縦の竹に沿って、紐を波のように通していきます。
頭の中は、ただ紐を通すことだけ。
誰も声を発さず、黙々と手を動かす時間。
まるで瞑想をしているかのような、静かなひとときが流れていました。


こちらは、土壁づくりのための“土プール”。
発酵のために混ぜ込んだ藁についていたお米が、なんと発芽していました〜。
竹小舞を編み終えたあとは、いよいよ土壁を練る作業の始まりです。
土に井戸水を加えたり、発酵をさらに促すために藁を切ったりするのですが、今回はなんと、だんじり祭りで使われた山車を引っ張る藁で編んだロープを切りました。
古民家の改修に使うものは、どれも地球からのいただきものばかりです(^^♪
左官職人さんからのリクエストで、横竹を編む際に必要な用具を自作している方もいました。
「買う」のではなく、「作る」。その姿勢にも心が温まります(^^♪
みなさん、今日もお疲れさまでした。
(YN)




